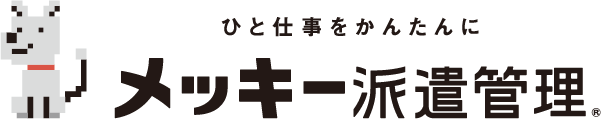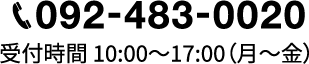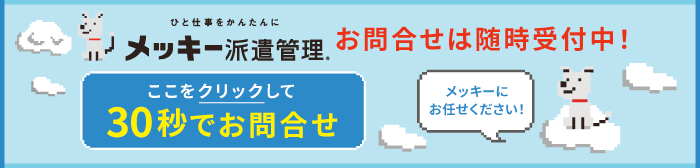2025年10月7日
2025年の年末調整の変更点:人材派遣管理システムでスムーズに対応!

年末調整は、従業員にとってはもちろん、人事・労務担当者にとっても毎年大きな業務負担となります。
特に、2025年の年末調整は、いくつかの法改正が重なることで、例年以上に複雑化することが予想されます。
「今年の年末調整は何が変わるの?」「何から手をつければいい?」と不安を感じているご担当者様も多いのではないでしょうか。
本稿では、2025年の年末調整で特に注意すべき変更点をわかりやすく解説します。さらに、これらの変更にスムーズに対応し、業務を効率化するためのポイントをご紹介します。
2025年 年末調整の主な変更点

2025年の年末調整は、いくつかの重要な法改正が適用されることで、例年とは異なる対応が求められます。
以下の3つの制度にて大きな改正が行われます。
・基礎控除の見直し
・給与所得控除の見直し
・特定親族特別控除の創設
担当者様は、これらの変更点を事前に正確に把握し、従業員への周知と準備を進めることが不可欠です。
ここでは、特に注意すべき3つの変更点について詳しく解説します。
1.基礎控除の見直し
2025年分の年末調整では、「基礎控除」の適用要件と控除額が見直されました。
所得水準に応じて控除額が変動する仕組みは従来と同様ですが、判定に用いる所得区分の方法が一部変更されています。
【改正の概要】
従来は、合計所得金額が2,400万円以下の納税者なら、誰でも一律で48万円の基礎控除が適用されていました。
これは非常にシンプルで分かりやすい仕組みでした。
改正後は、「一律」の考え方を大きく見直し、所得の少ない人ほど控除額が増える「段階的優遇」の仕組みへと変更されます。
具体的には、合計所得金額が2,350万円以下の方を対象に、所得に応じて58万円から最大95万円の範囲で段階的に控除されるようになります。
【改正のポイント】
合計所得金額132万円以下なら控除額が「ほぼ倍増」
この改正の最大のポイントは、低~中所得者層の手取り増加が期待される点です。
- 特に、合計所得金額が132万円以下の方(※)は、なんと最大95万円の基礎控除が認められます。
- これは従来の48万円からほぼ倍増にあたり、生活に必要な資金への課税を大幅に軽減し、税負担の軽減に直結します。
(※例えば、給与収入のみで年収約215万円以下の方などが該当します。)
【実務上の注意点】
従業員の所得区分把握が不可欠です。
企業や経理担当者にとっては、年末調整時に従業員一人ひとりの「合計所得金額」を正確に把握し、新しい区分表に基づいた適切な控除額を適用することが、これまで以上に重要になります。間違いのないよう、新しい控除区分をしっかり確認しておきましょう。
改正後の基礎控除額
| 合計所得金額 | 基礎控除額 |
| 合計所得⾦額132万円以下 | 95万円(改正前:48万円) |
| 合計所得⾦額132万円超336万円以下 | 88万円(令和9年分以後は58万円)(改正前:48万円) |
| 合計所得⾦額336万円超489万円以下 | 68万円(令和9年分以後は58万円)(改正前:48万円) |
| 合計所得⾦額489万円超655万円以下 | 63万円(令和9年分以後は58万円)(改正前:48万円) |
| 合計所得⾦額655万円超2,350万円以下 | 58万円(改正前:48万円) |
※特定支出控除や所得金額調整控除の適用がある場合は、上記金額と異なる場合があります。
2.給与所得控除の見直し:年収190万円以下の控除額が10万円アップ
「給与所得控除」は、会社員の方々の「みなし経費」として収入から差し引かれる控除です。
今回の改正は、特に年収が比較的低い層の手取りを増やすことを目的としています。
【改正のポイント】
最低控除額が10万円引き上げされます。
これまで、給与所得控除の最低保障額は55万円でした。
これが、今回の改正で65万円へと10万円引き上げられます。
この引き上げにより、以下の従業員の税負担が直接的に軽減されます。
- 対象者: 給与収入が190万円以下の従業員
- 効果: 控除額が一律65万円となり、所得税の計算のもとになる所得(課税所得)が減るため、税負担が軽減されます。
これは、低所得者層の生活を支援し、実質的な手取り収入を増やすための重要な措置です。
| 給与等の収入金額 | 給与所得控除額 |
| 190万円以下 | 65万円 |
| 190万円超 360万円以下 | 収入金額 × 30% + 8万円 |
| 360万円超 660万円以下 | 収入金額 × 20% + 44万円 |
| 660万円超 850万円以下 | 収入金額 × 10% + 110万円 |
| 850万円超 | 195万円 |
※給与収入が190万円を超える場合の控除額に変更はありません。
詳細な算式は国税庁の公表資料をご確認ください。
3.特定親族特別控除の創設:大学生のアルバイト収入による「扶養落ち」を緩和
2025年(令和7年)から、納税者の税負担を軽減し、特に大学生年代の子どもがアルバイトなどで稼ぎすぎることによる「親の扶養控除がなくなる」という問題を緩和するための新しい制度「特定親族特別控除」が導入されます。
【改正の概要】
この制度は、いわゆる「年収の壁」によって就業を控えていた19歳以上23歳未満の親族が、より働きやすくなることを目指しています。
1.創設の背景(従来の壁)
これまで、子ども(扶養親族)の合計所得金額が48万円(給与収入で103万円)を超えると、親は特定扶養控除(所得税63万円)を一切受けられなくなり、親の税負担が急増していました(これが「103万円の壁」)。
2. 新制度の対象者(特定親族)
「特定親族」とは、以下の条件をすべて満たす親族を指します。
| 項目 | 要件 | 従来の「壁」からの変化 |
| 年齢 | 12月31日時点で19歳以上23歳未満(大学生年代が中心) | 変更なし |
| 生計 | 納税者と生計を一にしていること | 変更なし |
| 所得 | 合計所得金額が58万円超123万円以下(給与収入で123万円超188万円以下)であること | 所得48万円の壁が、123万円まで段階的に緩和 |
3. 控除の仕組み:控除額が段階的に適用される仕組み
特定親族の合計所得金額が58万円(給与収入123万円)を超えても、所得が123万円(給与収入188万円)に達するまでは、その所得に応じて段階的に控除(最大63万円)が適用されます。
これにより、突然控除がゼロになる事態を防ぎ、親の税負担の急増を緩和します。
【実務上の注意点】
この控除は、自動的に適用されるわけではありません。
●新しい申告書の提出
納税者(従業員)は、年末調整時に「給与所得者の特定親族特別控除申告書」を提出する必要があります。
●扶養控除とは別
この控除は、特定扶養控除の対象外となった場合に受けるものです。
控除を受けるためには、この新しい申告書の提出が必須となります。
●企業担当者の役割
人事・労務担当者は、19歳から23歳の親族を持つ従業員に対し、制度の概要と申告書の提出漏れがないように周知徹底し、提出管理を確実に行うことが求められます。
変更点への対応:スムーズな手続きのポイント
2025年の年末調整における変更点は、担当者様の業務に直接的な影響を及ぼします。
特に、例年以上に複雑化が予想される手続きを、いかにして効率的かつ正確に進めるかが成功のカギとなります。
法改正への対応だけでなく、従業員とのコミュニケーションや、申告書の管理方法を見直すことで、業務負担を大幅に軽減できます。
ここでは、年末調整をスムーズに乗り切るための実践的な3つのポイントを解説します。
1.従業員への周知と情報収集
年末調整の変更点をいち早く従業員に周知することが最も重要です。
| 早めの情報提供 | 変更点をわかりやすくまとめた資料を配布したり、社内ポータルに掲載したりして、従業員に早めに情報を提供しましょう。 |
| 必要な書類の準備 | 従業員から提出してもらう必要書類(生命保険料控除証明書など)が何かを明確に伝え、準備を促しましょう。 |
2.申告書の記載内容チェック
申告書の記載漏れや間違いは、再提出や問い合わせの手間を増やす最大の原因です。
| チェックリストの作成 | 担当者が確認すべき項目をリスト化しておくと、見落としを防げます。 |
| 電子化の推進 | 手書きの申告書は、読み取りミスや記載漏れが発生しやすいです。電子化を進めることで、従業員がPCやスマートフォンから直接入力できるようになり、大幅な効率化が図れます。 |
3. 電子化の推進と業務効率化
複雑な法改正が重なることから、紙での手続きは担当者様の負担をさらに増やしかねません。
こうした課題を解決し、業務を抜本的に効率化する鍵が「年末調整の電子化」です。
単にペーパーレスになるだけでなく、多くのメリットが業務全体にもたらされます。
電子化がもたらす具体的なメリットは以下の通りです。
| メリット | 詳細 |
| 業務効率の大幅な向上 | 従業員がPCやスマホから直接入力できるため、紙の申告書を配布・回収する手間がなくなります。これにより、担当者の書類チェックやデータ入力業務が大幅に削減されます。 |
| 申告書の入力ミス・漏れの削減 | システム上で必須項目が自動チェックされるため、入力ミスや記入漏れが防げます。不備による差し戻しや確認作業が減り、スムーズに手続きが進みます。 |
| 進捗状況の可視化 | 誰がどこまで手続きを終えているかが、システム上でリアルタイムに確認できます。進捗が遅れている従業員への催促も簡単に行えます。 |
| ペーパーレス化によるコスト削減 | 印刷費や郵送費、書類保管スペースが不要になります。物理的な書類の管理負担がなくなることで、紛失リスクも軽減します。 |
| 法改正への迅速な対応 | 2025年の扶養控除の変更など、複雑な法改正にもシステムが自動でアップデートするため、担当者が最新の情報を個別に確認・反映する必要がなくなります。 |
これらのポイントは、2025年の変更点に対応するだけでなく、来年以降の年末調整業務にも役立ちます。
特に、電子化は一度導入すれば、その後の業務を劇的に効率化します。次項では、これらの課題をすべて解決し、年末調整をスマートに完結させるための具体的なソリューションとして、当社の派遣管理システムをご紹介します。
年末調整を効率化する「メッキー派遣管理」の活用
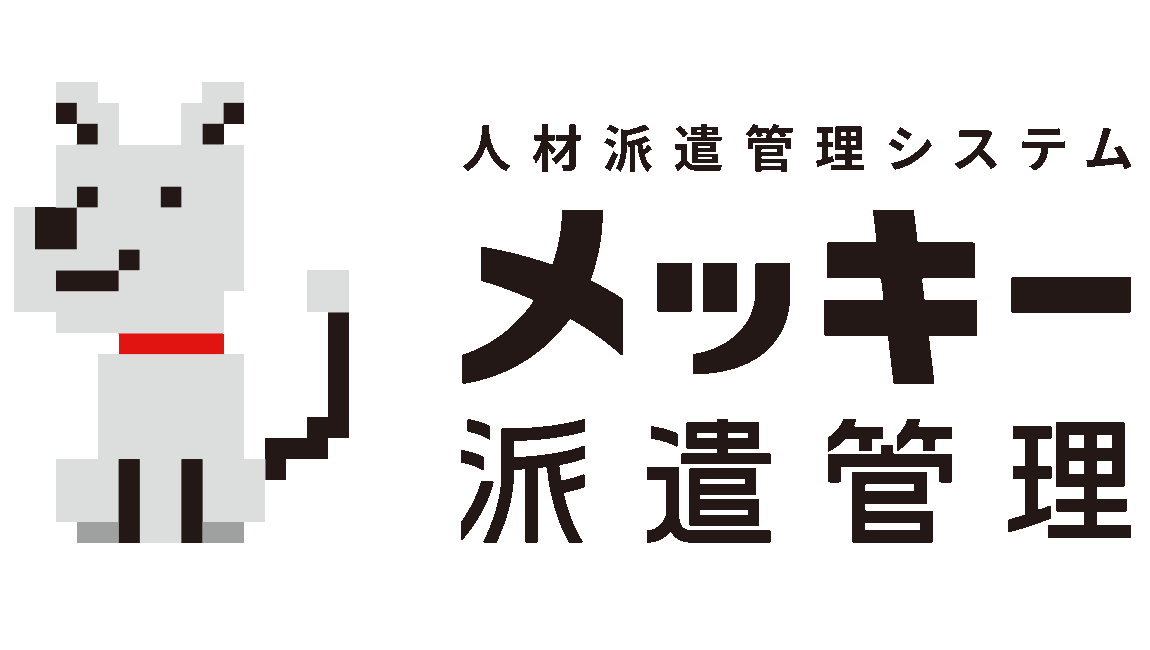
これらの課題を解決し、年末調整をスムーズに行うためには、ITツールの活用が不可欠です。
2025年の年末調整は、例年以上に多くの変更点があり、担当者様の負担が増えることが予想されます。
「メッキー派遣管理」は、勤怠管理から給与計算、さらには年末調整に必要なデータ収集・計算までをトータルでサポートするシステムです。
複雑な年末調整業務を効率化し、担当者様の負担を軽減するお手伝いをします。
1.情報集約と書類管理の効率化
年末調整に必要な扶養家族情報、生命保険料控除、地震保険料控除などの情報を、管理者がシステム上でまとめて管理できます。
提出書類は引き続き紙で回収しますが、システム上で従業員情報や控除内容を確認・整理できるため、記入漏れや転記ミスを防ぎ、確認作業の手間を大幅に軽減します。
紙の管理とデータ管理を併用することで、実務に即した運用が可能です。
2.法令改正への自動対応
税制改正や年末調整のルール変更は毎年発生します。メッキー派遣管理は、最新の法令に自動でアップデートされるため、常に正確な税額計算が可能です。
ご担当者様は、複雑な法令を一つひとつ調べる必要がありません。
3.年末調整書類の自動生成
従業員が入力した情報に基づき、源泉徴収票や各種控除申告書を自動で作成できます。
これにより、手作業による転記ミスを防ぎ、書類作成にかかる時間を大幅に削減します。
年末調整は、従業員の満足度にも直結する重要な業務です。メッキー派遣管理では、法令遵守をサポートしながら、バックオフィス業務を効率化し、企業の生産性向上に貢献します。
年末調整業務のデジタル化にご興味のあるご担当者様は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
まとめ 2025年 年末調整をスムーズに乗り切るために
2025年の年末調整は、例年以上に多くの変更点があり、担当者の皆様にとって大きな負担となる可能性があります。
しかし、変更点を事前に把握し、適切な対策を講じることで、業務をスムーズに進めることができます。
特に、従業員の勤怠情報や給与情報が正確に管理されていれば、年末調整の計算や書類準備は格段に楽になります。
「メッキー派遣管理」は、勤怠管理から給与計算、さらには年末調整に必要なデータ収集・計算までをトータルでサポートするシステムです。
複雑な年末調整業務を効率化し、担当者様の負担を軽減するお手伝いをします。百聞は一見にしかず。
2025年の年末調整を乗り切るツールとして、「メッキー派遣管理」がどれほど役立つか、ぜひ無料トライアルでお確かめください。
無料プランのお申し込みはこちらから!